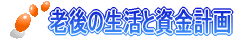贈与税の基本
相続税がかかる3つのパターン
物や権利を他人に贈与する場合は贈与税がかかってきます。特にこの贈与税は税率が高めに設定されて、税額の負担が大きくなっていますので、どのような時に贈与税の対象になって、贈与税がどれほどかかるのかを事前に確認しておくことが大切になります
![]()
誰が相続できるのか?・・法定相続人
贈与税の課税方法は、「暦年課税・相続時精算課税」の2種類あり、子供が贈与を受ける場合はこの2種類のうち、お得な方を選択できるようになっています。
ここでは従来からある、暦年課税の贈与税の税率と、税額の計算方法を説明しています
![]() 贈与税の税率と控除額(暦年課税)
贈与税の税率と控除額(暦年課税)
| 税 率 | 控除額 | |
| 〜199万円 | 10% | - |
| 200万円〜299万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円〜399万円 | 20% | 25万円 |
| 400万円〜599万円 | 30% | 65万円 |
| 600万円〜999万円 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円〜 | 50% | 225万円 |
[ 贈与税計算方法 ]
「(贈与された財産の価格-基礎控除(一律110万円)-配偶者控除(最高2,000万円))×税率-控除額=贈与税額」
具体的には、「贈与財産800万円・配偶者控除無し」の場合・・・
「(800万円-110万円)×40%-125万円=151万円」
となります・・・18.9%
また2人から贈与された場合、「贈与財産500万円+贈与財産700万円」の場合・・・
(500+700-110)×50%-225万円=320万円・・・26.7%
となり、かなりの高い税率となります
 贈与税の対象となる財産
贈与税の対象となる財産
金銭・土地・建物・宝石などの他に貸付金・営業権」などの経済的価値のあるものや、実際には贈与を受けていない、いわゆる”みなし贈与財産”なども、贈与税の対象となる場合があるのです
- 著しく低い価格で財産を譲り受けた場合(5,000万の家を500万円で譲り受けたなど)
- 基礎控除(一律110万円)以上の借金を免除してもらった場合
- 返済する能力がない、または返済する気がないのに、親から基礎控除(一律110万円)以上のお金を借りた場合など
- 保険契約者(父)・満期保険金受取人(子供)
- 親の所有する不動産を子供名義で登記した
- 土地等をローンの残高と共に譲り受けた場合は、その土地等の価額から引き継いだローンの残額を差し引いた残りが贈与税の対象となります
 贈与税がかからない財産
贈与税がかからない財産
- 扶養義務者から受けた教育費、生活費
- 香典、歳暮、お見舞いなどの金品
- 公益事業を行う者が譲り受けた公益事業用の財産
- 障害者、またはその扶養義務者が譲り受けた財産
- 相続税の対象となるもの
[ 贈与税の配偶者控除 ]
- 婚姻期間20年以上
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与された不動産に居住し、その後もその不動産に居住予定の場合
- 同じ配偶者から贈与税の配偶者控除を受けたことがない
贈与税の基礎控除110万円をプラスすると、合計で2,110万円までは非課税となります
 贈与税の節税対策
贈与税の節税対策
生命保険の契約で満期保険金の受取人が保険契約者と異なる場合は贈与税がかかりますので、できるだけ保険契約者と満期保険金受取人を同一にします
また死亡保険金の場合は保険契約者・被保険者・死亡保険金受取人の全てが異なる場合も贈与税がかかりますので注意しましょう
[ 贈与税の節税対策]
基礎控除110万円を上手に利用します
(例1)
1,000万円の贈与を1回で行うと・・・
1,000万円-110万円×40%-125万円=231万円の贈与税がかかります
(例2)
100万円-110万円=-10万円となり法律上は非課税となります
(例3)
120万円-110万円×10%=1万円の贈与税がかかります
例1はそのまま税金がかかってしまいますが、例2なら贈与税は課税されません。しかしこれは課税逃れとみなされますので、例3を基本に、毎年少しづつ金額を変えて贈与すると良いと思います