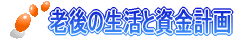退職金の所得税
退職金にも、所得税と住民税がかかりますが、これを軽減する措置がありますので、必ず利用するようにします。会社勤めのサラリーマンの方ですと、会社側から手続きの案内があるはずです。
退職所得控除と呼ばれ「退職所得の受給に関する申告書」を提出するだけで、確定申告の必要もなくなります。
仮に未提出のままですと、一律20%の所得税が源泉徴収されてしまいます(退職後に確定申告すれば還付は受けられます)
[ 退職所得控除額 ]
勤続20年以下:勤続年数×40万円 (上限80万円)
勤続20年以上:(勤続年数−20年)×70万円+800万円①
![]()
[所得税率]
〜195万円 : 5%(控除無し)
〜330万円 :10%(控除額 97,500円)
〜695万円 :20%②(控除額427,500円③)
〜900万円 :23%(控除額636,000円)
〜1,800万円 :33%(控除額1,53,600円)
1,800万円〜 :40%(控除額2,796,000円)
<試算>
勤続35年 退職金2,800万円の場合
・退職所得控除額 (35年-20年)×70万円+800万円 上記①
=1,850万円
・課税対象額 (2,800万円-1,850万円)×0.5(必ず0.5を乗じます)
=475万円
・所得税 475万円×20%(上記②)
=95万円-42.7万円(上記③)
=52.3万円
退職後の住民税
退職金にかかる住民税は、従来の給料受け取り時と同様に退職金を受け取る時点で既に源泉徴収されています。
定年退職すると、給与から特別徴収される予定だった住民税が残ってしまいますので、未納分が発生した場合、退職時に清算しなければなりません(退職時の給料から全て天引き清算されますから、特に何も手続きする必要はありません)。
しかし、退職後はもう給料から天引きされませんので、各自で住民税を納める必要があります。
退職の翌年6月に自宅に住民税の納入通知書が送付されてきますので、その納入通知書に従い納入するようにします。
再就職した場合などは、これまでどおり給料からの天引きになります(源泉徴収)
![]()

住民税は前年の収入を基に計算されますが、退職前年に大きな収入があった場合、支払いが高額になります。
逆にその後、収入が無くなれば翌年の住民税はゼロになります。
 |
会社を辞めるときの手続き マル得 ガイド 土屋 信彦      by G-Tools |